| 日本雑学辞典 |
| あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や・わ行 ら行 TOPへ |
| さ | |||
| 西郷さんの銅像 | 月代 | 刺身 | 三面記事 |
| 鮭(さけ) | 三拍子 | サバを読む | 差し金 |
| し | |||
| 塩 | じゃんけん | 白無垢 | 処女 |
| 七福神 | 質屋 | 菖蒲(しょうぶ) | しゃらくさい |
| 修羅場 | 食堂車 | 女子大生 | 資生堂 |
| 酒池肉林 | しがらみ | 地獄耳 | 白羽の矢 |
| 四苦八苦 | しっちゃかめっちゃか | しみったれ | 助手席 |
| す | |||
| スッポン | スイカ | すてばち | |
| せ | |||
| 切腹 | 成人式 | 正座 | セックス教団 |
| 関の山 | 正露丸 | ||
| そ | |||
| そばかす | 糟糠の妻(そうこう) | ソーラン節 | |
| 西郷さんの銅像 | |||
上野公園にドドン!とある西郷さんの銅像 着物を着用し兵児帯(へこおび)を締めて犬を連れとります 実はこの犬はウサギを狩るときに使う猟犬で、名前は「ツン」とい薩摩犬であります お利口さんだったらしいですよ この西郷さんの銅像を作ったのは明治を代表する彫刻家の高村光雲(こううん)という人で、高村光太郎のお父さんであります。 が、出来上がった銅像を見た西郷どんの奥様は「似てないわ!」と怒ったらしいですヨ〜 |
|||
| 月代(さかやき) | |||
昔の男性の髪型といえば月代 チョンマゲをして、頭のてっぺんを青々と剃っていました なんでそんな頭してんの?というと、このヘアースタイルはまさに「武士スタイル」なのであります 戦う時は鎧兜を着用しますが、兜は重くってしかもムンムンする ということで、少しでも涼しくする為に剃ってたんですね〜 江戸時代になると、兜をかぶるよーな戦いはないんですが、武士の心意気として「いつでも出陣するぜ!!」という意味合いを込めてました ちなみに月代をそるのは主君がいる人、つまり侍だけ ということで、ある意味「ステータス」だったんですね 浪人や町人とは違うぜ★みたいなね が、町人の間にも徐々に広まり、みーんなあの髪型になっていったのでした |
|||
| 刺身 | |||
ワタクシもダイスキなお刺身 お醤油&わさびで食べるようになったのは江戸時代後期から それまではしょうがなんかを混ぜたお酢で食べてました 切った魚なんで「きりみ」と呼ばれてたんですが、武士が「切る」という言葉を使うのは嫌じゃない?ってことで、「刺身」もしくは「おつくり」と呼ぶようになったんですね〜 |
|||
| 三面記事 | |||
新聞の三面記事といえば、社会面のこと ゴシップや下世話ネタが多いというイメージであります なんで三面記事っていうのさ?というと、実は明治時代の新聞は四面しかなかったんです 一面が広告 二面が政治経済 三面が社会面 四面は家庭や文化記事といった構成でした その名残が今も残り、社会面の記事のことを「三面記事」と呼ぶようになったのでした |
|||
| 鮭(さけ) | |||
鮭は石器時代からモリモリ食べられていた魚であります 東北にある貝塚からは鮭の骨粉が層ができるほど出てきました が!!古墳時代になると鮭はぱったりと姿を消してしまったのです ところが平安時代になるとわんさかと鮭が登場! うーん・・・。鮭の身に一体何が起きたんでしょうねぇ??? |
|||
| 三拍子 | |||
三拍子揃ってる!!などと、褒め言葉に使いますが、三拍子とはなんなのか?? それは「小鼓・大鼓・笛」のこと この三つの楽器でリズムをとることを三拍子というのであります で、この三つの楽器の拍子が上手に揃うと「三拍子揃ってる」ということなのでした |
|||
| サバを読む | |||
ちょろまかすことを「サバを読む」と言いますが、「サバ」とはお魚のサバであります 江戸時代、サバは大量に獲れました。むしろ獲れすぎて困ったほど ということで、全然ありがたくない魚だったのです だからサバの数なんかいちいち数えてられない そこからモノを数える時に数をごまかすことを「サバを読む」と言うようになりました おいしい魚なのにねぇ〜 |
|||
| 差し金 | |||
差し金とは歌舞伎の小道具のことです 舞台上で蝶をひらひらと飛ばす時に、差し金という金属の棒の先に蝶をつけ、陰で差し金を使い操っていたのです このことから、お客さんに見えないように陰で何かを操ることを差し金と言うようになりました |
|||
| 塩 | |||
人間の体に欠かせないのが「塩」 日本でも塩はとーっても大事なものでした が、日本には岩塩がなかったので、昔は海水から塩をとってました 縄文時代にも塩を作る道具が発見されています それくらい古くから塩は大切だったんですね〜 奈良時代になると塩一升に対して米二升というくらい塩は高価なものに 塩は貴重なものだったので、塩を大事にするために漬物や塩魚なんかができてきたんですね ちなみにお給料を「サラリー」といいますが、語源は「塩」 ローマでは軍人のお給料が塩で支払われていたからなのでした |
|||
| じゃんけん | |||
もともとのは中国の「本拳」が由来 江戸・元禄時代に日本に伝わってきて改良されました 日本版じゃんけんは「三すくみ」をもとにしてます 三すくみとゆーのは・・・ 蛙(グー)はヘビ(パー)を恐れヘビ(パー)はナメクジ(チョキ)を恐れ、ナメクジ(チョキ)は蛙(グー)を恐れるというものであります |
|||
| 白無垢 | |||
そもそも結婚式というのは、女性が神に仕えるという儀式 白装束というのは、神に接近できる資格を持った人が着るものなのです だから神の前では、女性は純白の装束に身を固め、頭には純白の角隠しをつけるのです ちなみに男性は何を着てもいい もともと、神とつながることができるのは女性だけという風俗があるからです よく花嫁が白い装束を着るのは「嫁いだ家の色に染まるため」という俗説がありますが、こちらは残念ながら嘘であります さらに補足すると、「お色直し」は白無垢から色つきのドレスや着物に替えますよね? あれは神に仕えていた女性が、今度は人間になって戻ってきましたよーという意味なのであります 人間の女に戻ったということで、祝い酒などを飲んでどんちゃん騒ぎしていいですよ!ということなのです |
|||
| 処女 | |||
日本は、「処女」を大事にするという意識はない国でありました 布教のため戦国時代にやってきた外国人も「日本は処女を大事にしなさすぎ!」というほど とても性に関してはあっけらかんとした国だったのです が、性に対してはあっけらかんとしても「血」に対してはかなり神聖な気持ちがありました 「処女」というのをこだわるようになったのは、明治時代の男尊女卑教育からであります ちなみに、「処女膜」という言葉を初めて使ったのは解体新書で知られる杉田玄白です |
|||
| 七福神 | |||
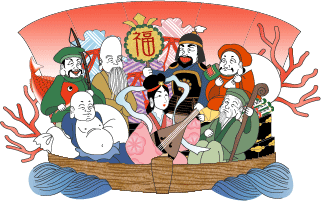 七福神を信仰するようになったのは江戸時代初期頃 七福神を信仰するようになったのは江戸時代初期頃が、実はこの七福神の出身地はまさに様々なのであります 簡単に書いちゃいましょう 恵比寿・・・日本 弁財天・・・インド(ヒンズー) 布袋・・・中国 大黒天・・・インド(仏教) 毘沙門天・・・インド(仏教) 寿老人・・・中国 福禄寿・・・中国 なんと、日本の神様は恵比寿さんだけだったんですね〜 |
|||
| 質屋 | |||
奈良時代から農作物の代わりに金銭を貸すということはありましたが、職業として出来たのは鎌倉時代のころ 質屋ではなく「土倉(どくら)」と言いました 当時は武士相手の商売でしたが、江戸時代になると庶民にも広まりました |
|||
| 菖蒲(しょうぶ) | |||
子供の日に菖蒲をお風呂に入れる風習が日本にあります 菖蒲は邪気を払う薬草として昔から用いられていました 武家社会になってくると、日本は「尚武(しょうぶ)」の国として、武を重んじてきたため、掛詞で菖蒲の人気もますます出てきたそうです |
|||
| しゃらくさい | |||
「しゃらくさいヤツめ」みたいな感じで使用する言葉ですが、こちらは遊女用語であります 遊女の上クラスは「伽羅(きゃら)」という高級な香を焚きこめていました そこへ野暮なお客さんがジャコウの安っぽい匂いでやってくると、香が混ざって「伽羅っぽい匂い」に変化 この「伽羅っぽい」がなまってきて「しゃらくさい」と呼ぶように 昔は野暮な人のことを「しゃらくさい」と言ったのであります |
|||
| 修羅場 | |||
修羅場というのは、帝釈天(たいしゃくてん)と阿修羅(あしゅら)が戦った場所のことです 阿修羅は仏教の守護神である帝釈天に敗れ、悪行を懲らしめられてしまいました ということで、悪い意味での修羅場をくぐった人というのは、最後は勝ち残ることはできないんですよ〜 |
|||
| 食堂車 | |||
食堂車が出来たのは明治32年5月25日 山陽鉄道が始まりであります その2年後、東海道本線にもできました ちなみに当時のメニューはというと・・・ 食蒸餅・・・・ショクパン 6銭 ビーフステーキ・・・10銭 などなど ワタクシ、一度も食堂車でご飯を食べたことないので、一度は北斗星とかに乗って食べてみたいですな〜 |
|||
| 女子大生 | |||
日本で初めて女子大生が誕生したのは大正2年 現在の東北大学が、女性の受験生3人の合格を発表したのであります 当時は女性が大学に行くのはものすごーーーいコトだったんですよ〜 |
|||
| 資生堂 | |||
化粧品メーカーの資生堂の創業は明治5年 創業した時は西洋学の調剤薬局でした 資生堂という名前は、中国の古典「易経」にある「万物資生」という言葉からとったもの 万物はここから生まれるという意味であります |
|||
| 酒池肉林 | |||
酒池肉林といえば、お酒を浴びるほど飲み、回りには美女がいっぱい・・・・というイメージがありますが・・・・ 酒池肉林を夢見ていた方、残念でした〜(笑) 酒池はあってますが、「肉林」というのは女性のことじゃないんですね〜 食べ物の肉が林のように大量にあることであって、女性の体とは全く関係ないのであります |
|||
| しがらみ | |||
何かと色んなしがらみがある現代人 そんな「しがらみ」とは一体何か?というと、・・・ もともとは水の流れをせき止めるため、川に杭を打ち、そこに竹を何本も置いた柵のこと しがらみとは、上流から流れてきた色んな物が絡みつくものだったのです そこから、しがらみとは「まといつくもの」という意味が生まれました たまには自分自信の「しがらみ」を掃除した方がいいかもね(笑) |
|||
| 地獄耳 | |||
江戸時代、「地獄」というのは一般の人間生活とは別の知るはずもない世界のことを指してました。 たとえば娼婦が多くいる宿は「地獄宿」と呼ばれてました 他人の秘密とか、普通なら耳にするはずのないことなどを知ることができたのです こっから「地獄耳」という言葉が生まれました ほんとは、地獄耳ですね〜なんて言われたら、相手は自分のことを薄気味悪く思ってるってものだったんです |
|||
| 白羽の矢 | |||
白羽の矢とは、古来日本でいけにえを求める神が目当ての娘の家に白い羽のついた矢を立てたことに由来します なぜ白なのか?とういと、昔から天皇の乗る馬は白馬とされていたように、白は最上の色とされていたからです |
|||
| 四苦八苦 | |||
四苦八苦とは仏教用語です 四苦とは「生・老・病・死」の四つの苦しみのこと 八苦とは「愛別離苦(あいべつりく)怨憎会苦(おんぞうえく)求不得苦(ぐふとくく)・五陰盛苦(ごおんじょうく)」のこと これを全部まとめたのが「四苦八苦」で、人間のありとあらゆる苦しみを現した言葉なのです とういことで、「んもーーー。仕事が忙しすぎて四苦八苦してるよ!!」といった程度の苦しみは、四苦にも八苦にも入らない程度なのであります(^^;) |
|||
| しっちゃかめっちゃか | |||
もともとの語源は芝居の世界で使われていた「しっちゃか面子」 この言葉は隠語で、ブスな女性を指した言葉だったのであります それが次第にめちゃくちゃっていう意味に使われるようになりました |
|||
| しみったれ | |||
お金を持ってるくせにケチケチしたりすることを「しみったれてるなぁ」と言いますよね これは江戸時代、とあるお金持ちがシミのついた着物を着ていたことから始まります 貧乏人は「おいおい、あの人金持ちのくせにあんなシミのついた着物きてるぜ」」と、陰口を叩きました シミがついた着物を着てるのが貧乏人ならゴマンといるんですが、金持ちだったってことがポイントなんですね〜 こおから、金持ちのくせにけちけちしてるよーなことを「しみったれ」と言うようになったのでした |
|||
| 助手席 | |||
運転席の隣の席を助手席といいますが、この語源はタクシー用語であります 大正時代のタクシーには、運転手のほかにもう1人、お客さんの乗り降りをお手伝いする人がいたんです で、この人たちは「助手さん」と呼ばれていて、ここから助手席という言葉がうまれたんですね〜 |
|||
| スッポン | |||
スッポンは江戸時代の超高級食材でした スッポンは弥生時代から食べられていて、文武天皇の時にはスッポンを奉るお祭りまでありました 補足ですが、フグはよく当る(毒があるから)ってことで「鉄砲」と呼ばれていて、スッポンは「まる」と呼ばれていたようですよ〜 |
|||
| スイカ | |||
スイカが日本にやってきたのは南北朝時代 が、めっちゃ嫌われていました スイカを割ると赤い果肉だったのでまるで斬首のイメージ 大きさも頭くらいだったしね ということで、みんな気味悪がっていました 江戸時代までは下々が食べるものされていたのでした |
|||
| すてばち | |||
自暴自棄になってだらけた生活を送ってるような状況を「すてばちになる」と言いますが、「すてばち」という言葉はお坊さん用語であります 禅宗の托鉢からきた言葉で、僧の修行の一つとして鉢を持って街角に立つことがあります 寒い日も暑い日も修行するのですが、この辛さにガマンできなくなり鉢を捨てて逃げ出してしまう僧も多くいました ここから「すてばち」という言葉が生まれたのでした |
|||
| 切腹(せっぷく) | |||
切腹は日本特有の自殺行為であります おなかを斬って死ぬなんてめちゃくちゃ痛そうです・・・ なぜおなかなのか?というと、昔の人は魂はおなかの中にあると信じていたんです 心臓を刺したり、首を刎ねた方がひとおもいに死ねるのに、なかなか死ねずにものすごく痛い思いをする「ハラキリ」は、武士独特の死に様でもあります 武士にとって「切腹」とは、その痛さに耐えられるくらい、武士らしく豪気さを残して死にたいというデモンストレーションでもあったのでした ちなみに日本第一号の「切腹人」は、988年に死んだ泥棒の袴垂保輔(はかまだれやすすけ)という人 源頼光に追われ、これ以上逃げとおすことはできないと覚悟し、腹を刺し、でもって腸を引き出したとのことです |
|||
| 成人式 | |||
最近の成人式は何かとお騒がせが多いですが、日本では昔から成人を祝う儀式がありました 現在のように20歳ではなく、男子は15歳 女子は13歳あたりになると「ゆもじ祝い」「ふんどし祝い」などという名前で行われました 男子は前髪をそり落とし、女子はお歯黒をしたりと地域によって祝い方はさまざま 戦後の昭和23年になって現在の「成人の日」となったのです |
|||
| 正座 | |||
礼儀正しい座り方とされている正座 が、正座が礼儀正しいとされるのは300年前に茶の湯が流行してからなのであります 当時の茶室は狭いため、正座しないと皆が入れなかったため「正座」が定着したのであります では、ほんとーーーの礼儀正しい座り方は??というと、正座になる前は「あぐら」だったのです 平安時代の男性の着物の足の部分が大きくなってるのは、あぐらしやすいためなんですね〜 女性はというと、方膝をたてるという座り方が正式なものだったのでした |
|||
| セックス教団 | |||
宗教とセックスは切っても切れないようです・・・・ 日本で初めてのセックス教団は鎌倉時代のこと 「立川流」というものです 本来は真言密教の流れを汲んでいるんですが、ここのここの教えは性行為によって人間の魂が救われるというもの これが大流行! 正統派の真言宗の人気ががた落ちになってしまうほど すごいのが人間の頭蓋骨を使うというコト 頭蓋骨をご本尊にして、セックスした後の和合の水(・・・・わかるかな・・?)を頭蓋骨に塗りたくると救われるとされていました が、次第に正統派の真言宗から「これは邪教だ!!」とブーイングの声があがり、消えていきました |
|||
| 関の山 | |||
人の能力の上限とか、精一杯なし得る限界を指す時に使われる「関の山」 「あいつの頭じゃ○○大学が関の山だろ」みたいなね 実はこの「関」というのは三重県の関町のこと 「山」とは、祭りのダシ(山車)のことなのであります 関町の八坂神社のお祭りに出す山が「これ以上贅沢はない」ってくらいすっごいモノだった ここから、なし得る限界をあらわす言葉として「関の山」という言葉が生まれたのであります |
|||
| 正露丸 | |||
実は、もともとの名前は「征露丸」 その名のとーり、ロシアを征服するという意味が込められております 正露丸は、日露戦争の時に日本兵士に配られた胃腸薬だったのです ラッパのマークは軍用ラッパなのであります 戦後になって現在の「正露丸」に変えることになりました |
|||
| そばかす | |||
「そばかす」という言葉が出来たのは江戸時代 江戸ギャルにとって、めっちゃ嫌なことは「そばかす」が出来ることでした 肌に出来る小さな斑点が、そばの実を粉にする時に残るそばのカスに似ていることから「蕎麦粕=ソバカス」と呼ばれるように そばかすを漢字で書くと「雀斑」 「雀斑」という漢字が当てられたのは、色や形が雀の斑点にも似ているからであります |
|||
| 糟糠の妻(そうこうのつま) | |||
山内一豊の妻・千代などが「糟糠の妻」と言われますが、糟とは酒かすのこと。 糠とはぬかのことであります 酒かすもぬかも粗末な食べ物なので、ここから苦難を乗り越えともに歩んできた妻のことを「糟糠の妻」と言うようになりました |
|||
| ソーラン節 | |||
もともとは漁師の掛け声であります ソーランとういのは「ソラ ソラ」の掛け声が変化したもの 北海道でニシン漁が行われていた時に歌われる様になりました 当時 縦網法という漁法が行われてました 方法は、ニシンでいっぱいになった網を母船まで引っ張っていき、タモ網で母船に積み替えるというもの この積み替え作業が一番大変で、このときにソラ!ガンバレ!ソラ!ソラ!と掛け声を掛け合いました これがやがてソーランになったのでした |
|||